福祉医療制度
野迫川村では子ども・心身障害者・ひとり親家庭の人に対して健康の保持増進を図り、生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的として、医療費の助成をおこなっています。助成の対象者は、野迫川村に住所を有する健康保険の加入者で、各要件に該当する者です。
子ども医療費助成事業
対象者
[通院・入院]
0歳~18歳(18歳になる年度の属する3月末まで)
(0歳~高校卒業まで)
申請に必要なもの
印鑑、金融機関の通帳、マイナ保険証(または資格確認書)等の身元確認書類
申請(更新)は原則毎年1回です。既に医療証をお持ちの方には申請書を役場から送付しますので、必ず更新の手続きをお願いします。
所得制限
所得制限はありません。
助成内容
医療保険の適用される最終的な自己負担額を助成します。
(入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
助成金の支給方法
医療機関窓口にて受給資格証を提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。
助成金は後日登録口座に振り込まれます。
令和6年8月診療分からは高校卒業までの子どもの医療費窓口負担については現物支給(注)になりました。
(注)県内の医療機関に受給資格証を提示すると、その場で減額されます。
領収証と印鑑を持参し役場窓口にて助成金を請求してください。
助成金は後日登録口座に振り込まれます。
心身障害者医療費助成事業
対象者
1歳以上(後期高齢者医療被保険者・生活保護受給者を除く)で1級・2級の身体障害者手帳所持者、
または療育手帳A1 ・A2所持者
(身体障害個別級が3級以下であっても、総合級で2級以上であれば該当します。)
申請に必要なもの
印鑑、身体障害者手帳または療育手帳、金融機関の通帳、マイナ保険証(または資格確認書)等の身元確認書類
申請(更新)は原則毎年1回です。既に医療証をお持ちの方には申請書を役場から送付しますので、必ず更新の手続きをお願いします。
所得制限
本人、その配偶者及び扶養義務者で主としてその者の生計を維持するものについて、前年の所得(1月から7月までの間に受けた心身障害者の医療費については前々年の所得)が、以下の制限額を超えないこと。
旧国民年金法施行令に定める老齢福祉年金の支給制限額
助成内容
医療保険の自己負担額から定額(低額)の一部負担金(※)を除いた額
(ただし、入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
(※)一部負担金
- 通院については、1医療機関につき、1か月あたり500円
- 入院については、1医療機関につき、1か月あたり1,000円
(2週間未満の入院の場合は、500円)
1歳から18歳(18歳になる年度の属する3月末まで)の方の一部負担金は、ありません。
(入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
助成金の支給方法
医療機関窓口にて受給資格証を提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。
助成金は後日登録口座に振り込まれます。
令和6年8月診療分からは高校卒業までの子どもの医療費窓口負担については現物支給(注)になりました。
(注)県内の医療機関に受給資格証を提示すると、その場で減額されます。
高校卒業までの子どもの受給資格証…………水色
高校卒業までの子ども以外の受給資格証……白色
県外の医療機関を受診したとき(県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったとき)
領収証と印鑑を持参し役場窓口にて助成金を請求してください。
助成金は後日登録口座に振り込まれます。
ひとり親家庭等医療費助成事業
対象者
次のいずれかに該当する者。(後期高齢者医療制度該当者及び生活保護受給者を除く)
ア.配偶者のない女子で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
(以下「対象児童」という。)を現に扶養している者
イ.配偶者のいない男子で対象児童を現に扶養している者
ウ.ア又はイに掲げる者に現に扶養されている対象児童
エ.父母のない対象児童
オ.エに掲げる者を現に養育している配偶者のない女子、婚姻をしたことのない女子、
配偶者のない男子又は婚姻をしたことがない男子
申請に必要なもの
印鑑、金融機関の通帳、マイナ保険証(または資格確認書)等の身元確認書類
申請(更新)は原則毎年1回です。既に医療証をお持ちの方には申請書を役場から送付しますので、必ず更新の手続きをお願いします。
所得制限
前年所得(1月から7月までの間に受けたひとり親に関する医療費については、前々年の所得とする)が児童扶養手当法施行令に規定する額未満であること。
- 本人所得制限基準額の適用範囲……………父、母又はこれに準じる者
- 扶養義務者等所得制限基準額の適用範囲…子、子の配偶者、父又は母及び子の扶養義務者
助成内容
医療保険の自己負担額から定額(低額)の一部負担金(注)を除いた額
(ただし、入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
(注)一部負担金
- 通院については、1医療機関につき、1か月あたり500円
- 入院については、1医療機関につき、1か月あたり1,000円
(2週間未満の入院の場合は、500円)
対象児童については、一部負担金はありません(入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
助成金の支給方法
県内の医療機関を受診するとき
医療機関窓口にて受給資格証を提示し、医療費の自己負担分を支払ってください。
助成金は後日登録口座に振り込まれます。
令和6年8月診療分からは高校卒業までの子どもに限り医療費窓口負担は現物支給(注)になりました。
(注)県内の医療機関に受給資格証を提示すると、その場で減額されます。
高校卒業までの子どもの受給資格証…………水色
高校卒業までの子ども以外の受給資格証……白色
県外の医療機関を受診したとき(県内の医療機関で受給資格証を提示しなかったとき)
領収証と印鑑を持参し役場窓口にて助成金を請求してください。
助成金は後日登録口座に振り込まれます。
重度心身障害老人等医療費助成事業
対象者
65歳以上の後期高齢者医療制度加入者で心身障害者医療費助成制度該当者、または
75歳以上のひとり親家庭等医療費助成制度該当者
申請に必要なもの
印鑑、身体障害者手帳、金融機関の通帳、マイナ保険証(または資格確認書)等の身元確認書類
申請(更新)は原則毎年1回です。前年度対象者の方には申請書を役場から送付しますので、必ず更新の手続きをお願いします。
所得制限
心身障害者医療費助成事業・ひとり親家庭等医療費助成事業の対象者と同じ
助成内容
医療保険の自己負担額から定額(低額)の一部負担金(注)を除いた額
(ただし、入院時の食事療養費に係る標準負担額を除く)
(注)一部負担金
- 通院については、1医療機関につき、1か月あたり500円
- 入院については、1医療機関につき、1か月あたり1,000円
(2週間未満の入院の場合は、月500円)
助成金の支給方法
医療機関窓口にて自己負担分を支払ってください(生活保護受給者は除きます)。
助成金は登録口座に後日振り込まれます。
この制度には受給資格証はありません。マイナ保険証(または資格確認書)を必ず提示してください。
医療機関の適正受診にご協力お願いします!
医療費助成の費用は、皆さまの大切な税金で賄われています。
・医療費が高くなる夜間や休日の受診はできるだけ避けましょう。
・病院の重複受診はやめましょう。
・ジェネリック医薬品を活用しましょう。
・一人ひとりが日々の健康管理を心がけましょう。
- このページに関するアンケート
-
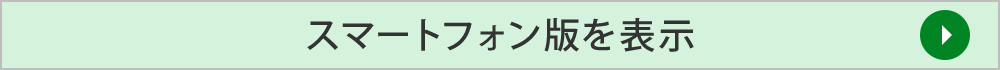








更新日:2025年08月13日