介護保険
介護保険制度について
高齢による身体機能の衰えや、病気やケガなどによって介護が必要になったときは、介護サービスを利用することができます。介護保険制度は、平成12年にスタートした、介護が必要な人とその家族をできる限り社会全体で支えるための公的なサービスです。
要介護(要支援)認定の申請について
被保険者が日常生活に支援が必要な状態になったとき、役場住民課に要介護(要支援)認定の申請をします。
申請後、調査員が訪問し心身の状況などを聞き取りながら確認し、全国共通の調査票に記入します。また、役場から主治医に意見書を依頼します。
介護認定審査委員会が調査票に基づいた一次判定結果や主治医の意見書などをもとに、介護の必要性とその程度の判定をします。
認定の対象者
•第1号被保険者(65歳以上の方)
•第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
(注意)2号被保険者の方は、国が定めた16種類の特定疾病が原因で、介護が必要な状態となった場合に限ります。
申請できる人
介護を必要とする本人または、その家族など
要介護認定の種類
•要支援1 •要支援2
•要介護1 •要介護2 •要介護3 •要介護4 •要介護5
•非該当
要支援1・2、または非該当と認定された方
地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアマネジメントを行います。
要支援1・2と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。
また、非該当と認定された方は、村が行う地域支援事業の介護予防事業を利用することになります。
どちらのサービスも地域包括支援センターが中心となって、住みなれた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートしていきます。
要介護1から5と認定された方
要介護1から5と認定されると、介護サービスを利用できます。
実際に利用を開始する前に、居宅介護支援事業者と契約し、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプラン(居宅サービス計画)を作成することが必要となります。
介護サービスの種類
在宅サービス
在宅サービスには、居宅を訪問してもらう訪問系サービスや施設に通って受ける通所系サービスなどがあります。
「要介護1~5」と認定された人は、まず居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)に依頼して、利用するサービスを具体的に盛り込んだ居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
「要支援1・2」と認定された人は、地域包括支援センターが中心となって、介護予防ケアプランを作成し、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。
|
サービス一覧 |
|
|
居宅介護支援 |
ケアマネージャーが、利用者に合った「ケアプラン」を作成し、そのプランに沿って安心してサービスを利用できるように、利用者を支援します。 |
|
訪問介護 |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事・入浴・排せつなどの身体介護や、炊事・掃除などの生活援助を行います。 |
|
訪問入浴介護 |
介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護をします。(村内に事業所はありません。) |
|
訪問看護 |
疾患などを抱えている人について、看護師などが居宅を訪問し、主治医の指示に基づく看護が受けられます |
|
訪問リハビリテーション |
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。(村内に事業所はありません。) |
|
居宅療養管理指導 |
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします |
|
通所介護 |
通所介護施設で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための支援を日帰りで行います。(村内に事業所はありません。) |
|
通所リハビリテーション |
介護老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。(村内に事業所はありません。) |
|
短期入所生活介護 |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に短期間入所して、日常生活上の支援(食事、入浴、排せつなど)や機能訓練などが受けられます。 |
|
短期入所療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。 |
|
特定施設入居者生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活上の介護や支援を提供します。 |
|
福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。 |
|
特定福祉用具販売 |
都道府県の指定を受けた事業者から対象の福祉用具を購入したとき、購入費が支給されます。申請が必要です。 |
|
住宅改修費の支給 |
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に利用者負担の割合に応じた額が支給されます。 事前の申請が必要です。 |
施設サービス
施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。
※要支援の人は、施設サービスは利用できません。
|
施設の種類 |
|
|
介護老人福祉施設 [特別養護老人ホーム] (原則、要介護3以上の方) |
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。 |
|
介護老人保健施設 [老人保健施設] |
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。 |
|
介護療養型医療施設 |
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。 |
|
介護医療院 |
主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。 医療と介護(日常生活上の世話)が一体的に受けられます。 |
地域密着型サービス
地域密着型サービスでは、住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じた地域の特性に応じたサービスが受けられます。原則として、他の市区町村の地域密着型サービスは利用できません。
|
サービス一覧 |
|
|
認知症対応型共同生活介護 (要支援2から要介護5の方) |
認知症高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。 |
|
認知症対応型通所介護 |
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 |
介護保険料について
第1号被保険者(65歳以上の方)
世帯や個人の所得などに応じて13段階に分けられ、所得の少ない方の負担が重くならないように配慮されています。また、介護保険事業計画の見直しに伴い3年ごとに見直されます。第1号被保険者の介護保険料は、野迫川村の介護サービスにかかる費用などから算出された「基準額」をもとに、皆さんの前年の所得に応じて決まります。
第9期介護保険料(2024年度から2026年度)野迫川村の基準額は(年額)76,140円、(月額)6,345円。所得段階別の保険料は下表のとおりです。
| 国の標準段階(13段階) | 基準額に対する割合 | 保険料 (月額) |
保険料 (年額) |
|
| 第1段階 | ・生活保護被保護者・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 | 0.455 (0.285) |
2,887 (1,808) |
34,644 (21,696) |
| 第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 | 0.685 (0.485) |
4,346 (3,077) |
52,152 (36,924) |
| 第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超 | 0.69 (0.685) |
4,378 (4,346) |
52,536 (52,152) |
| 第4段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円以下 | 0.9 | 5,711 | 68,532 |
| 第5段階 | 本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人年金収入等80万円超 | 1 | 6,345 | 76,140 |
| 第6段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額120万円未満 | 1.2 | 7,614 | 91,368 |
| 第7段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 | 1.3 | 8,249 | 98,988 |
| 第8段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 | 1.5 | 9,518 | 114,216 |
| 第9段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 | 1.7 | 10,787 | 129,444 |
| 第10段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 | 1.9 | 12,056 | 144,672 |
| 第11段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 | 2.1 | 13,325 | 159,900 |
| 第12段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 | 2.3 | 14,594 | 175,128 |
| 第13段階 | 市町村民税課税かつ合計所得金額720万円以上 | 2.4 | 15,228 | 182,736 |
第1号被保険者(65歳以上の方)の方の保険料の納め方
特別徴収
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している方は、年金から天引きされます。 普通徴収
特別徴収以外の方は、口座振替または納付書により役場や銀行・郵便局などで納めます。
※特別徴収から普通徴収納、または普通徴収から特別徴収への変更はできません。
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)
給与の額や所得金額等に応じて金額が決定され、加入されている健康保険・組合・共済等の医療保険料等と一緒に納付します。
保険料を納めないでいると
特別徴収
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給している方は、年金から天引きされます。 普通徴収
特別徴収以外の方は、口座振替または納付書により役場や銀行・郵便局などで納めます。
※特別徴収から普通徴収納、または普通徴収から特別徴収への変更はできません。
野迫川村第10期高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画を作成しました
- このページに関するアンケート
-
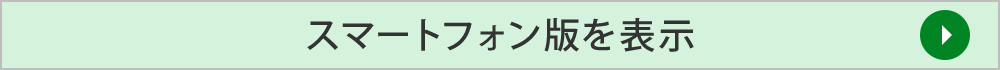








更新日:2024年05月24日